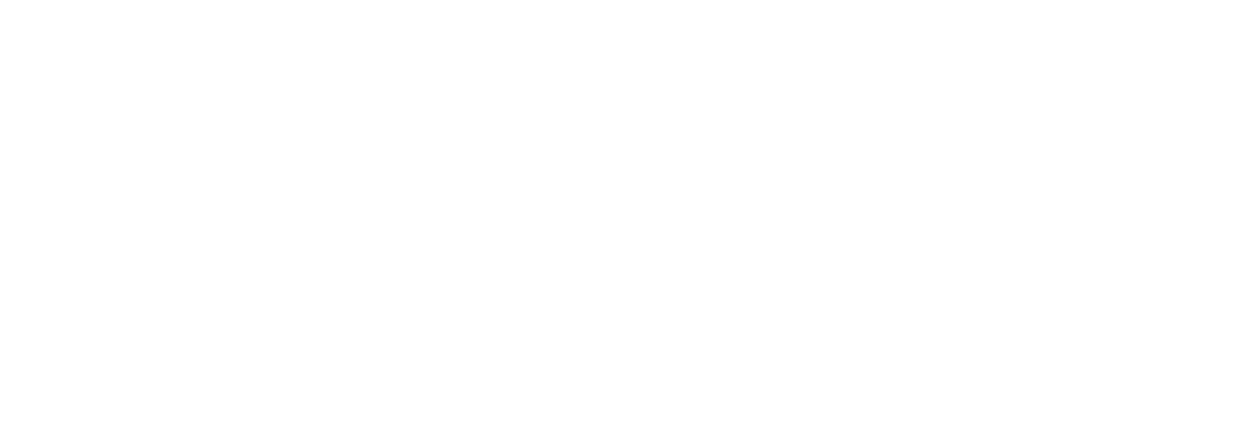村上春樹の短編連作小説 『神の子どもたちはみな踊る』を映像化した『アフター・ザ・クエイク』。NHK連続テレビ小説『あまちゃん』などで知られる井上剛監督がメガホンを取った本作は、1995年の阪神・淡路大震災から2025年の現代まで、30年にわたる日本社会の変化を4つの時代で描いた意欲作だ。岡田将生、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市の主演で、原作の4編にオリジナル要素を加え、それぞれ異なる時代・場所で喪失感を抱える人々の物語が交錯していく。10月3日(金)から公開される本作について、井上監督に話を聞いた。
Contents
震災をテーマにする理由─「真正面から取り組めないテーマ」への向き合い方
「震災をテーマに活動し続けているわけではないんですよね。なかなか自分でも自分に説明できてないんですけど」。そう語る井上監督だが、『その街のこども』「あまちゃん」『LIVE!LOVE!SING!~生きて愛して歌うこと~』「いだてん~東京オリムピック噺~」に続き、今回で5作目となる震災関連作品への思いは複雑だ。
きっかけは、大阪放送局時代のプロデューサーからの「震災を題材にドラマをやってくれないか」という依頼だった。「当然僕はそういう経験はしてないし、自分にはとてつもないと思った。真正面から取り組んで、被災した人に何かを届けるわけじゃないですか、何かを作るということは。そんなこと、ドラマではできない」と、当初は躊躇していたという。
しかし、『その街のこども』で震災から10年以上経った神戸を離れた男女を描いて以降、震災は監督にとって避けて通れないテーマとなった。「最初は行きがかり上だったけど、だんだん自分にとっても大事なテーマになってきている」

村上春樹の文学を映像化する困難─「文学の豊かさを損なわずに」
原作となった『神の子どもたちはみな踊る』は、実は『その街のこども』制作時から井上監督が読んでいた作品だった。しかし、「当時は当然、この原作を15年後にやろうなんて思っていなかった。だけど、今ならできるかもしれない」という思いで挑戦に至った。
「文学の豊かさを損なわずに、読んだ時に誰もが持っている読後感を大切にしたかった。ただ文字をそのまま映像に起こしたからってそうはならない」。映像と文学の間にあるものをどう埋めるかが最大の課題だった。
特に困難だったのは、原作に共通する「からっぽ」という感覚の映像化だ。「岡田さんが『からっぽなんだ』って言ってるけど、そういう男として演じなきゃいけない。セリフの中にはそんな理不尽なセリフ一つもないのに、からっぽに見せなきゃいけないって相当難しい」。
監督は地下鉄の場面では模型を作成し、様々なアングルから撮影。乗客を合成することで独特の「奇妙さ」を表現した。「少しずつ見る人に連想と想像をしていってほしい。皆が地下に潜ったような、自分の意識下に入っていくような感じになれたらな」という狙いがあった。4つの時代の物語が廊下で1つになるシーンも30年の時代のうねりを表現している。


30年の時の流れを描く─オリジナル要素で現代に繋げる
原作から大きく変更したのは時代設定だ。原作では1995年に集約されていた物語を、1995年、2011年、2020年、2025年の4つの時代に分けて描いた。
「25年前の原作なんだけれども、なぜそれを今やるのかというと、やっぱり現代の人に届けたいし、現代の自分が見たいものになった方がいい」。1995年の阪神・淡路大震災から始まり、2011年の東日本大震災、2020年のコロナ禍を経て2025年の現代へ。「1995年はそこから揺れが起きたというふうになった。人間の揺れも含めて、それがどう波及して次の時代に迫っていくか」という構造にした。
この時代設定の変更により、『アフター・ザ・クエイク』というタイトルは「何かのafterは、次に起きる何かのbeforeでもある」という意味を持つ。「あれは何かの前触れだったのかもしれない」という想像力を観客に委ねる仕掛けだ。

キャストとの創作過程─「分からなさ」を共有した現場
岡田将生、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市など実力派キャストたちとの撮影は、通常の映画とは異なる雰囲気だったという。
「一様にみんな『難しい、分からない』と言っていた。でも分からなさをむしろ求めてきている感じもある」。特に岡田将生の演技について、「からっぽに見せなきゃいけないって相当難しい。どうやったらそんなことができるんだろう。でも実際にいますよね。真っ当で何も間違ってない、だけどからっぽっていう人って」。
一方、佐藤浩市だけは例外だった。「佐藤さんは唯一、人間を相手にしてない人。他の人は人間を相手にしてるから分からない。でも佐藤さんはかえるくんを相手にしてるから、実は楽なんですよ」。


希望はどこにあるのか─絶望ではない物語として
一見すると希望の見えにくい物語だが、井上監督は「絶望的な物語をやった感じはない」と語る。
「すごく分かりやすい希望を提示しているわけではないけれど、例えば1章の岡田さんのラストだって『でも、まだ始まったばかりだから』って言われることをどう受け止めるかは人によって違う」。
2章では「朝が来たら自然に目が覚めるという台詞があるので、2人は震災から助かったんだと僕は思っています」。3章では「神など、いろんな呪縛から解放されていって」、4章では佐藤浩市さん演じる片桐が「自分なりの戦いをしてきた感じがする。区切りをつけたという意味でも、清々しささえありました」。


「“揺れているもの”を感じ取ってもらいたいですね」と監督は語る。「この30年とか生きてきた人ならば、今だから思えることとかあるだろうし、この作品の中に揺れているものを感じ取っていただけたら」。
上海国際映画祭での上映時、中国の観客から「日本ってそんなに地面が揺れるんですね」という感想があったという。「そういう揺れの上にずっと生きている国民だと意外に知られていない」。
災害が日常化してしまった現代日本への問題意識も込められている。「毎年のように不幸な目に遭う人がいっぱいいることに対して慣れてきてしまっている。その人にとっては一生に一回起きたことなのに」。そうした想像力を映画を通じて取り戻してほしいという願いがある。
「世の中、分からないことの方が実は圧倒的に多いんですよね。分からないところで地震が起きて、どうにもできないわけじゃないですか」。井上監督は、分からないことを分からないままに受け入れる勇気の大切さを語る。
30年という時の流れの中で、私たちが見失ってしまったものは何か。震災という「揺れ」が与えた影響は何だったのか。本作は、答えを提示するのではなく、問いかけ続ける映画として、観客一人一人の内面に語りかけてくる。
『アフター・ザ・クエイク』は10月3日より、テアトル梅田、なんばパークスシネマ、MOVIX堺、MOVIX八尾、アップリンク京都、シネ・リーブル神戸、MOVIXあまがさき他にて公開。
インタビュー・文:ごとうまき