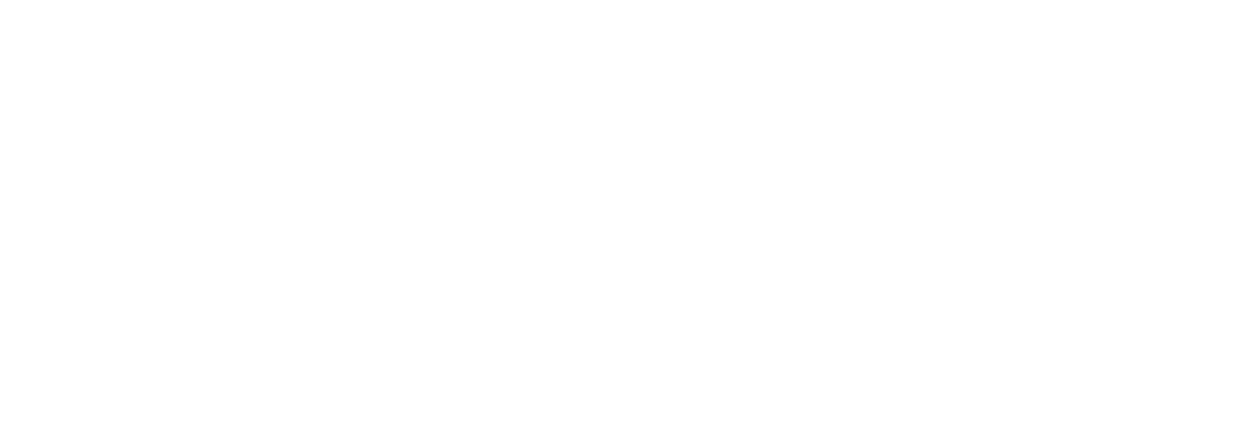黒澤明監督の伝説的名作が、現代の舞台に再び蘇った。大阪・新歌舞伎座にて2025年12月14日(日)まで上演中の舞台『醉いどれ天使』である。終戦直後の東京の“焼け跡”に、今の世界の“瓦礫”を重ね合わせ、普遍的な人間の営みと、生死の有り様を深く描く胸を衝かれる衝撃作だ。
舞台の概要と物語
本作は、世界的な名匠・黒澤明と名優・三船敏郎が初めてタッグを組んだ1948年の同名映画を原作としている。特筆すべきは、映画公開の半年後に上演された黒澤明氏によるオリジナルの舞台台本が奇跡的に発見され、それを継承している点である。この台本を基に、2021年に続き新たなキャスト・スタッフで2025年版として再演された。
物語の舞台は、すべてが失われ、荒廃した終戦直後の東京の闇市である。
ある晩、闇市の顔役である若きヤクザ・松永(北山宏光)が、酒に溺れ口は悪いが腕は一流の町医者・真田(渡辺大)の診療所を訪れる。松永は肺病に侵されていた。真田は治療を強く勧めるが、松永は聞く耳を持たない。
診療所に住み込む美代(佐藤仁美)や、松永に密かに想いを寄せる幼馴染のぎん(横山由依/岡田結実・Wキャスト)が彼の体調を案じる中、松永の病状は悪化していき、ダンサーの奈々江(阪口珠美)は彼から離れていく。また、兄貴分・岡田(大鶴義丹)の出所が、闇市の力関係に波乱を巻き起こすのだ。暴力と物質が流れ込む混沌とした闇市で、生きることに精一杯な人々の葛藤と運命が、濃密に描き出される。



現代に熱く突きつける深作健太の演出意図と生命のテーマ
演出を手掛けるのは、深作欣二監督の息子である深作健太氏である。深作氏は、作品の舞台である1947年頃の日本の“焼け跡”に、ガザをはじめ世界中で起きている戦争の“瓦礫”を重ねるという、鋭い視点を導入した。モノローグや生演奏を多用することで、戦争という厄災がもたらす深い悲しみと、それに対峙する人間の生のエネルギーを、観客にダイレクトに伝えてくる。
本作は、「命を繋ぐ」という言葉で簡単に語り尽くせるものではないが、極限状況における生死の有り様や、生きる苦しみ、そしてその中に見出す生き抜く素晴らしさが、登場人物一人ひとりの描写を通して深く描かれている。


戯曲の根幹をなす「モノローグ」と人間性
脚本を手がけた蓬莱竜太氏は、原作映画の演劇的なセリフに着想を得て、戯曲の基礎となる登場人物のモノローグ、特に女性の視点からのモノローグを導入した。ヤクザの松永を演じる北山宏光さんの演技は、荒々しさとは異なり、病に蝕まれながらも威厳を保とうとする極めて繊細な内面を表現しており、真田(渡辺大)と共に“酔いどれ天使”として、敗戦によって「前向きになれない男達の悲しみと屈折」を露わにする。
一方で、舞台は女性たちの強さを鮮烈に描く。真田の診療所に住み込む美代(佐藤仁美)ら女性たちは、虐げられていた時代の中で、いかにして生きようとしたのか——この作品からは、いつの時代も、女性が世を動かしているのだと痛感させられる。
混沌と絶望が渦巻く闇市で、沼から這い上がることのできない人々にやがて訪れる絶望の淵から差し込む一筋の光。そう、いつの時代も、若者や子どもが希望である。「どん底でも希望を捨ててはいけない」という力強いメッセージが、観客の心に強く突き刺さる。


今年は戦後80年という節目を迎え、ドラマや映画、舞台などでも多くの戦争をテーマにした作品が世に出ている。この舞台は、その中でも特に、闇市という泥沼の中で絶望感に苛まれながらも命を燃やし続けた人たちの生き様を、フィジカルでエネルギッシュな表現を満載に描いている。
戦争を経験された方々がどんどん少なくなる今だからこそ、戦争を知らない私たちの世代、さらに若い世代へと、戦争の恐ろしさ、悍ましさを伝えていかなければならない。新たなキャストと、現代の危機意識を投影した演出による本作は、その重責を担うにふさわしい、時代を超えた普遍的な人間ドラマである。ぜひ、この機会に 新歌舞伎座(2025年12月14日(日)まで)で、この衝撃作をご自身の目でお確かめいただきたい。
舞台『醉いどれ天使』は、大阪・新歌舞伎座にて2025年12月14日(日)まで上演中。

撮影:宮川舞子/岩村美佳
文:ごとうまき