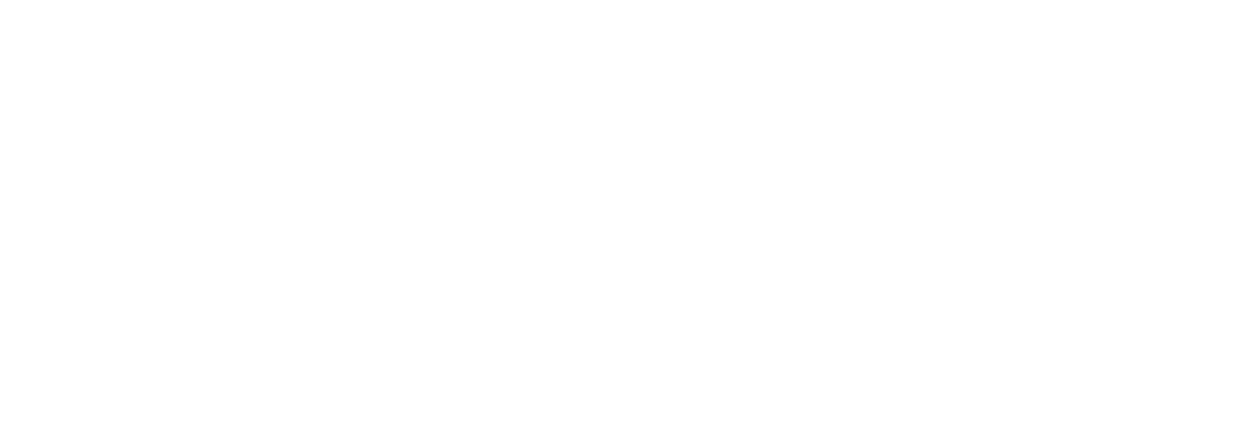かつて、これほどまでに「時間」そのものを主役として捉え、モノクロームの階調の中に閉じ込めた映画があっただろうか。PFF(ぴあフィルムフェスティバル)プロデュース作品として誕生した最新作『道行き』。メガホンを執ったのは、前作『おばけ』でPFFアワード2019グランプリを受賞し、スペイン・韓国・アメリカなど海外映画祭でも高く評価されている新鋭・中尾広道監督だ。
物語の舞台は、奈良県御所(ごせ)市。中尾監督自身がこの町の古民家に一目惚れし、移り住んだことからこの映画は動き出した。400年前の地図が今なお息づくこの場所で、監督は俳優・渡辺大知と、重要無形文化財保持者(人間国宝)・桐竹勘十郎という、映画の枠組みを超えた奇跡の共演を実現させた。
「空間を移動する旅ではなく、その場所に堆積した時間の層をめくる旅」。そう語る中尾監督は、なぜ彩り豊かな現代において、あえて白黒の世界を選んだのか。鉄道が運ぶ近代の足音、人形浄瑠璃文楽が紡ぐ普遍的な情念、そして古民家の柱一本に刻まれた記憶――。中尾監督の心の奥底に眠る「大切な風景」を解き明かす。
Contents
カラーを捨てた必然。地層をめくる「縦移動」の映像体験
―― 全編を通して綴られるモノクロームの世界観に圧倒されました。今回、奈良の風景をあえて白黒で描こうと決めた理由からお聞かせいただけますか?

―― 最初からモノクロ一択だったのでしょうか? それともカラーの可能性も?
劇中には、昭和二、三十年代の古い写真が登場します。あそこを基準として、過去を切り離されたものにするのではなく、現在と地続きで息づいている様を捉えたかった。境界を曖昧にし、過去・現在・未来の繋がりを見せるためには、全編をモノクロで統一することが必然でした。

©2025 ぴあ、ホリプロ、日活、電通、博報堂、一般社団法人PFF
人間国宝と渡辺大知。二つの個性が交差する
―― 舞台となった御所(ごせ)市は、400年前の地図を手に今も歩くことができる町だそうですね。移住の決め手は、劇中に登場するあの古民家だったとか。

―― その梅本役を演じられたのが、人間国宝の桐竹勘十郎さんです。映画初出演とは思えない圧倒的な佇まいでした。

―― 主人公・駒井役の渡辺大知さんとの距離感も絶妙でした。


©2025 ぴあ、ホリプロ、日活、電通、博報堂、一般社団法人PFF
400年の時を繋ぐ「文楽」と、近代の秒針とともに動く「鉄道」
――劇中では、文楽の演目『面売り』も登場します。タイトルも『道行き』と、文楽との深い繋がりを感じますが、監督ご自身も文楽がお好きだとか。
今回、御所でリサーチをしていた時に、『面売り』の演目とリンクするような昔の写真に出会いました。かつて商人の町として栄えた御所の賑わいを、文楽の演目を通して観客に想起してもらいたい。そんな思いから『面売り』のシーンを加えました。

10年越しの想いを乗せて。鉄道が刻む「近代」と「呼吸」
―― 鉄道のシーンは、窓の外の景色と車内の時計が連動し、観客を不思議な時間の旅へと誘います。撮影はかなり大変だったそうですね。

―― 鉄道会社の清水さんが、ご本人役で出演されているのも驚きました。

「昔は良かった」の先へ。スクリーンに刻まれた、消えゆく豊かさ
―― 監督ご自身も御所に移住されて4年になります。作品にはゆったりとした時間が流れていますが、ご自身の生活に変化はありましたか?


©2025 ぴあ、ホリプロ、日活、電通、博報堂、一般社団法人PFF
―― 最後に、この映画を通して伝えたいメッセージはありますか?

映画『道行き』
2026年2月13日㈮~ヒューマントラストシネマ有楽町、テアトル新宿
2月20日㈮~シネ・リーブル神戸
2月27日㈮~テアトル梅田
近日公開 ナゴヤキネマ・ノイ、京都シネマ ほか全国順次公開
公式サイト: https://www.michiyuki-movie.com/
出演者
渡辺大知 桐竹勘十郎
細馬宏通 田村塁希 大塚まさじ
上田隆平 梅本 修 清水弘樹 中井将一郎 中山和美 ちょび
監督・脚本・編集 中尾広道
プロデューサー 天野真弓
撮影 俵 謙太
照明 福田裕佐
録音・整音 松野 泉
美術 塩川節子
衣装 田口 慧
ヘアメイク 根本佳枝
助監督 内田知樹
音楽 『マカラプア』
バッキ―白片とアロハ・ハワイアンズ
テイチクエンタテインメント
『猫目唄』作曲 細馬宏通
題字 桐竹勘十郎
人形浄瑠璃 文楽『面売り』
作曲:野澤松之輔
協力 公益財団法人 文楽協会
一般社団法人 人形浄瑠璃文楽座
独立行政法人日本芸術文化振興会 国立文楽劇場
第28回PFFプロデュース作品
製作:ぴあ、ホリプロ、日活、電通、博報堂、一般社団法人PFF
制作プロダクション:エリセカンパニー
配給:マジックアワー
2025年/白黒/80分/DCP/ヨーロピアンビスタ
英題:Michiyuki -Voices of Time
インタビュー・文:ごとうまき