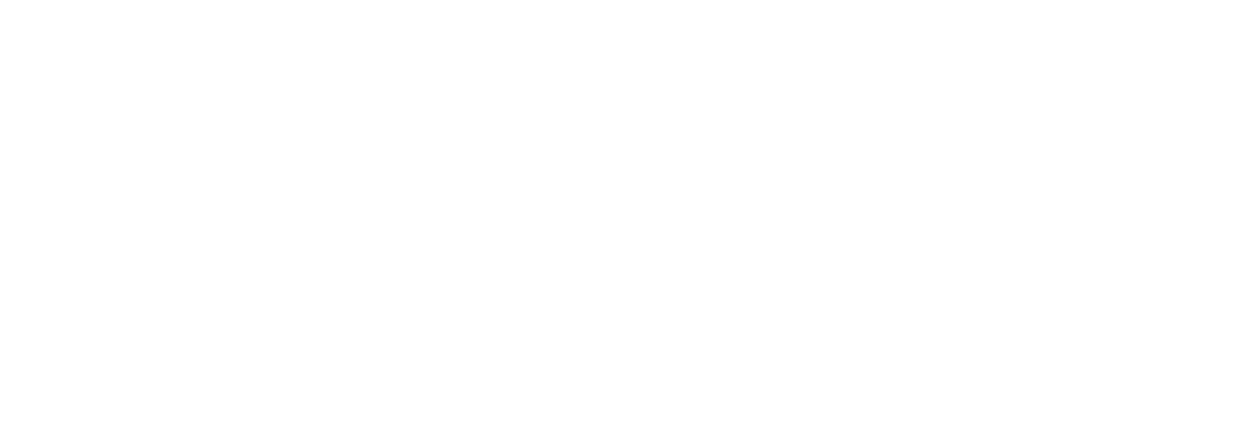『向日葵の丘 1983年夏』や『朝日のあたる家』など、骨太なテーマを丁寧に描いてきた太田隆文監督が、自身の壮絶な闘病体験を映画化しました。タイトルは『もしも脳梗塞になったなら』。17年間、脚本からプロデュースまで7人分の仕事をこなし続けた結果、脳梗塞、両目半分失明、心臓機能低下という危機に見舞われた監督。一命を取り留めた今、病という「悲劇」を「喜劇」としてスクリーンに映し出した真意を伺いました。
命がけの1週間撮影と、スタッフへの想い
── まず、エンドロールの構成に驚きました。通常はキャストの皆さんが先ですが、本作はスタッフの方のお名前が先に並んでいます。これは、監督の強いこだわりや、病を経験されたからこその変化した思いが込められているのでしょうか?

── これまで監督は脚本、プロデューサー、編集など7人分の仕事をしてこられたそうですが、今回は3人分(監督、プロデュース、脚本)に抑えられたとのこと。そして、通常の映画制作は1ヶ月から3ヶ月の撮影期間を要するところを、本作はわずか1週間で撮り終えられたそうですね。

── その連続で、ご自身としては、いつかガタが来るのではないかという危機感はなかったのでしょうか?

サラリーマン社会の断絶と、女性の社会性
── 映画化の動機の一つに、「脳梗塞の具体的症状を知る人が少ない」という危機感があったそうですね。監督自身も発症するまで具体的なことはご存知なかったと。

── 劇中では、主人公が病状を訴えても、サラリーマンの友人は「お前が病気?笑わせるな」と信じてくれないシーンがありました。この「病気への無理解」は、現代社会の象徴のように感じました。

── その流れで、男性と女性の社会性の違いについての鋭い指摘がありました。

── お母様への思いも強く描かれており、グッときました。

SNSの「光と闇」と、真の支援者たち
── 闘病中、SNSを通じて多くの人からアドバイスや支援が寄せられた描写もありました。的外れな助言や嫌がらせがある一方で、会ったこともない人からの食料支援もありましたね。

── その的外れな助言をする人たちの背景を、監督は「無力感」と分析されていましたね。

── 逆に、孤独死を回避できたのは、SNSを通じた意外な人たちからの支援だったとのこと。

── では、本当に役に立つ情報はどこから来たのですか?

── 劇中の喫茶店で、視覚に障害のあるスズメさんと会うシーンがありますが、あれは現実でも起こったそうですね。


悲劇を喜劇で描くチャップリンの精神と、新しい使命
── シリアスなテーマにもかかわらず、劇中ではマンボの音楽が流れるなど、全体にコミカルなタッチが散りばめられています。

── 主人公が死神とチェスをする夢のシーンでは、監督自身の「エンタメか社会派か」という悩みが表現されていました。

── キャスティングについてですが、主演の窪塚俊介さんは、師匠である大林宣彦監督の作品に出演されていたことが決め手の一つだったそうですね。佐野史郎さんは、かねてから出演を熱望されていたとか。

──劇中の舞台挨拶で話していた“ウォーレン・スパーン”のエピソードは、これまで7人分の仕事をこなしてきた監督が、初めて「人に頼ること」を受け入れた瞬間のように感じました。

── 最後に、現在の病状と、今後の活動について教えてください。

12月20日(土)より全国順次公開
大阪第七藝術劇場12月27日(土)~
兵庫キノシネマ神戸国際12月20日(土)~
京都アップリンク京都1月30日(金)~
インタビュー・文・撮影:ごとうまき