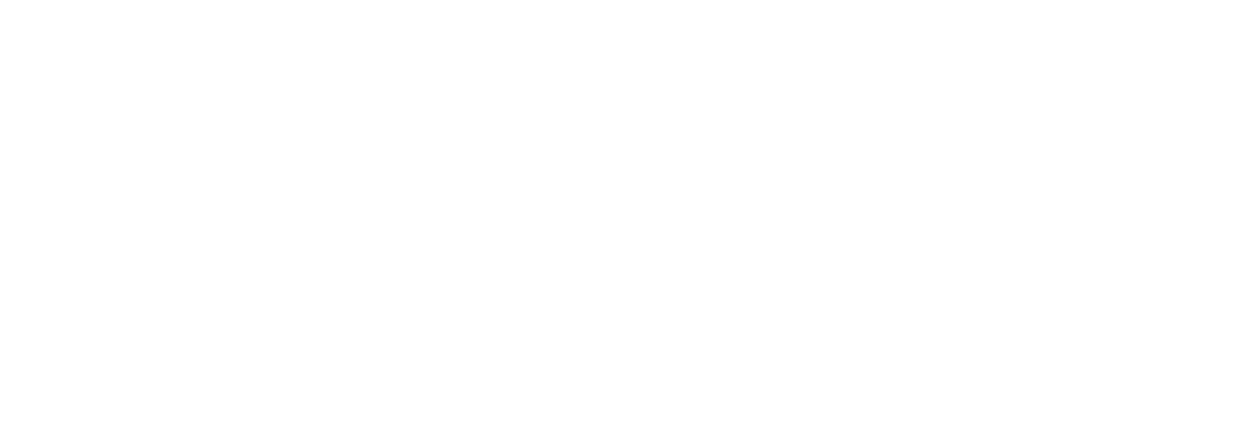日本のポピュラー音楽が大きな転換期を迎えた1970年代。その中心地の一つであり、今日の世界的なシティ・ポップ・ブームの源流ともなった伝説のレーベル「PANAM(パナム)」が、2025年に誕生55周年を迎えた。かぐや姫、イルカ、細野晴臣……、数々のスタンダード・ナンバーを世に送り出してきたこの歴史的レーベルの扉を今、一人の音楽家が再び開く。
その人の名は、佐橋佳幸。数々のミリオンセラーに携わり、日本の音楽シーンを最前線で支え続けてきた彼が、自ら「火元責任者」を名乗り始動させたのが、リメイクカバー・プロジェクト『PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS』だ。
「主役はあくまで楽曲」と語る佐橋氏。彼はなぜ今、自身が多感な時期に浴びるように聴いたというパナムの楽曲を、現代のアーティストたちと共に再構築しようとしているのか。盟友・Dr.kyOnとのユニット「Darjeeling」をサウンドプロデューサーに据え、徹底的に「いい歌」と「グルーヴ」にこだわった制作の舞台裏、そしてレジェンドたちとの交流から見えてきた「音楽の普遍性」について、熱く、深く語っていだきました。
Contents
「火元責任者」の原体験、ラジオとラジカセが教えてくれたもの
――今回のプロジェクト、発案は佐橋さんご自身だったと伺いました。まずはこの企画が動き出した経緯から教えてください。

――佐橋さんにとって、パナムというレーベルはどのような存在だったのでしょうか。
でも、ラジオをいじっていると日本の曲も流れてくる。クラスの連中はみんな、かぐや姫を聴いていて。僕はギターを始めたら意外とすぐに上達したもんで、「『22才の別れ』弾いてよ」なんて頼まれて弾いてあげたりしていましたね。 
――洋楽少年が日本のパナム作品に本格的に心奪われたきっかけは?

「楽曲が主役」名曲に纏わせる“令和の服”
――今回のプロジェクトは「楽曲が主役」というテーマを掲げています。選曲やキャスティングのこだわりは?

――続く第2弾、第3弾も非常にユニークな組み合わせですね。


デジタル時代に失われた「グルーヴ」を求めて
――第5弾の『都会』では、槇原敬之さんが大貫妙子さんの名曲を歌っています。ファンにはたまらない、特別なテイクですね。この豪華な共演はどのように実現したのですか?
この曲では「エレキ・シタール」という楽器を使っています。70年代のソウルミュージックでよく使われていた楽器で、これで“都会の夜の感じ”を表現したかった。大貫さん本人も途中から入ってくれて、槇原くんの歌を聴いて「ここはもうちょっと言葉を置いて歌って」とアドバイスをくれた。 
――今の若い世代もサブスクを通じてこうした古い名曲を聴いていますが、佐橋さんは今の音楽シーンをどう見ていますか。
もう一つ、今の音楽には「グルーヴ」が足りない。打ち込みで何でもできてしまうから、ドラマーがいないバンドも増えている。でも、ビートルズもストーンズも、すべてはドラマーが作るグルーヴから始まっていた。パナムの楽曲には、今の音楽が失いつつある「人間味」や「不自由さゆえの工夫」が全部詰まっているんです。 
黄金期の目撃者として、老人介護……ならぬ「先輩介護」の矜持
――佐橋さんは、パナム所属ではありませんが大瀧詠一さん、山下達郎さん、坂本龍一さんといった、まさにパナムが黄金期を築いていた頃の音楽シーンのど真ん中にいらっしゃった方々と共演されています。

――それは佐橋さんにしかできないことですよね。

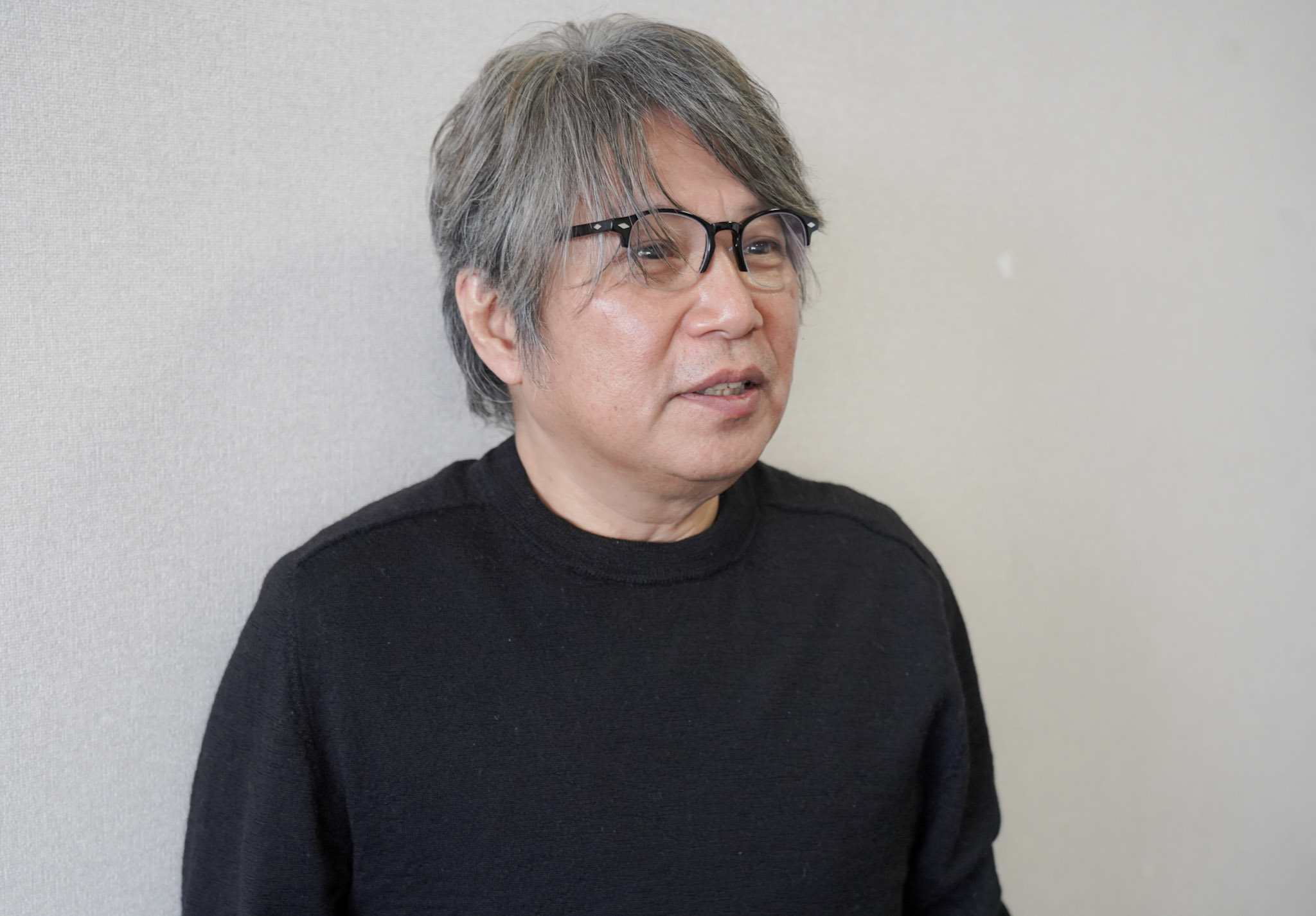
相棒・Dr.kyOnとの絆、そしてこれからのパナム
――サウンドプロデューサーのDr.kyOnさんとは、このプロジェクトでも最高のコンビネーションですね。

――プロジェクトはこれからも続いていきますが、今後の展望を教えてください。

インタビュー後記
「火元責任者」を自称する佐橋さんの言葉には、自身を育ててくれた音楽への深い敬意と、それを次世代へ繋げようとする強い使命感が溢れていた。最新のデジタル技術を使いながらも、あえて人間の内面の揺らぎや時代のエッセンスを注入するその手腕。パナム55周年の灯火は、彼の手によってさらに熱く、新しく燃え広がっていくだろう。
インタビュー・文・撮影:ごとうまき