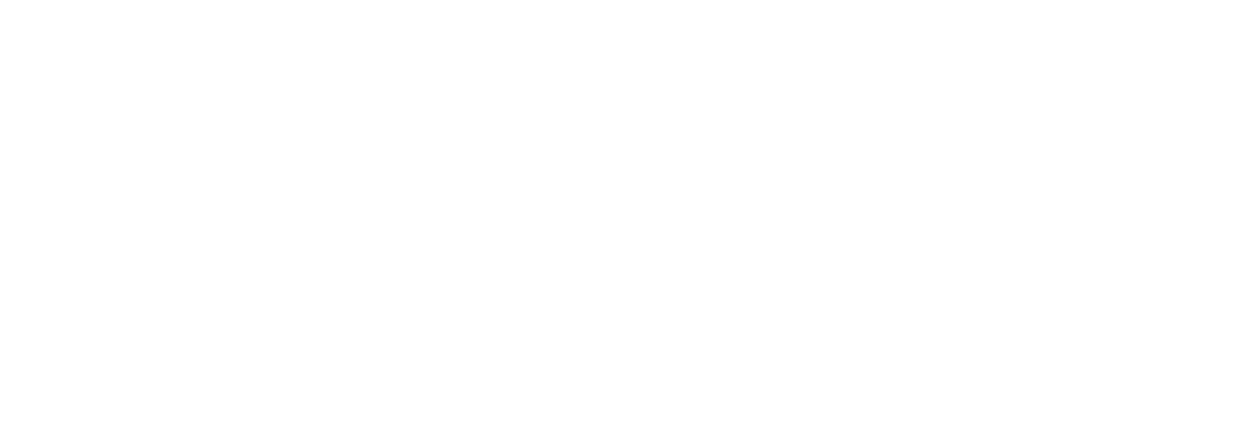『佐藤忠男 映画の旅』が2025年11月1日(土)より新宿K’s cinemaほか全国で順次公開中です。生涯にわたり映画を愛し、日本映画史の体系化やアジア映画の発掘に尽力した孤高の映画評論家、佐藤忠男(2022年逝去)。本作は、彼が学長を務めた日本映画学校(現・日本映画大学)の教え子である寺崎みずほ監督が、その知られざる素顔と、彼を突き動かした情熱の源泉を探るドキュメンタリー。関西での映画の公開を前に、監督に佐藤忠男の人物像、そして映画製作の道のりについて詳しくお話を伺いました。
映画学校での出会いと監督の原点
── まずは、この佐藤忠男さんのドキュメンタリーを制作されたきっかけについて伺います。寺崎監督は、実際に映画学校で佐藤先生の授業を受けられていたそうですね。先生はどのような印象でしたか?

── 監督が、そもそも映画学校に入られたきっかけは何だったのでしょうか?

取材開始の衝撃と妻・久子さんの存在
── 卒業されてから数年後、2019年に再会し、取材を申し込まれたのですね。取材をしたいと思われた具体的なきっかけ、佐藤さんの言葉を教えていただけますか?

── 映画の中で、奥様の久子さんの存在は非常に重要ですが、どのように描こうと決断されたのですか?

── 取材をしたいと伝えられた時の、佐藤先生の反応はいかがでしたか?

── 実際にお話をされていたのは、2019年から2020年の1月くらいまでで、その後コロナ禍になってしまったそうですね。

アジアへの眼差しとインド映画の魔法
── 佐藤先生はアジア映画の発掘・紹介にも尽力されました。監督は先生の死後、アジアの地へと旅立たれます。特にインドの旅は印象的でした。アジアに目を向けた経緯を教えてください。

── インドの旅では、奇跡的な偶然が重なったそうですね。

── 実際にケララ州を訪れて、『魔法使いのおじいさん』への印象は変わりましたか?



反骨精神とバトンを繋ぐメッセージ
── 映画を通して見えてきた佐藤先生の人物像で、最も監督が影響を受けていると感じる点は何でしょうか?

── 今回の製作で一番大変だったことは何でしょうか?

── この数年を通して、監督自身、映画製作への思いに何か変化はありましたか?

── まさに、佐藤さんの思いのバトンを繋ぐ作品ですね。最後に、もし天国の佐藤先生にメッセージを伝えられるとしたら?

『佐藤忠男 映画の旅』
* 公開日: 2025 年 11 月 1 日(土) 新宿 K’s cinema ほか全国順次公開
* 大阪公開: 12月13日(土) 第七劇場にて公開
インタビュー・文・撮影:ごとうまき