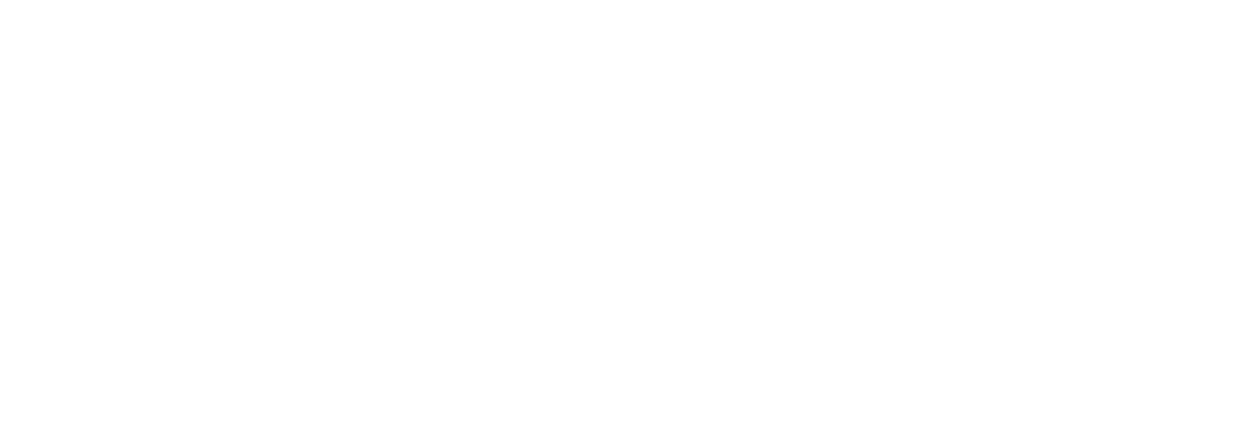静かな空間に、桂春蝶の声が響く。落ち着いた口調の中にも、落語家としての熱量と人生の重みが宿る。2025年11月26日(水)、関西で人気の落語家・桂春蝶、桂吉弥、そして江戸落語界の旗手・春風亭一之輔が一堂に会する「春蝶・吉弥と一之輔 三人噺 2025」が、SkyシアターMBSで開催される。
過去最大のキャパシティを誇るこの舞台で、3人の噺家がトリネタを披露する。吉弥は「蛸芝居」、一之輔は「らくだ」、そしてトリを務める春蝶は「紺屋高尾」を演じる。落語初心者からベテランまでを魅了する、贅沢な一夜だ。
3回の熱戦を振り返り、4回目へ
「三人噺」は2022年の初公演、2023年の昼夜2公演で計3回を重ねてきた。その始まりはMBSのプロデューサーからの提案だ。
「東京の噺家を入れたいという話で、一之輔くんに声をかけたんです」と春蝶は振り返る。
2022年の1回目は大盛況、2023年の2回目は即完売で追加公演が組まれるほどの熱狂だった。
「吉弥くんは同期だし、一之輔くんは東西の対比が面白い。みんな最前線でやってるから、どのポジションで出ても自分の印象をどう残すか、緊張感がすごいんですよ。でも、その緊張が血を熱くする。準備にかける時間、熱量が、いい結果を生むんです。」春蝶の目は、まるで高座の上で客席の視線を浴びる瞬間を思い描いているかのようだ。
4回目となる今回は、春蝶がトリを務める。
「これまでの3回で、みんなが作ってくれた流れがある。そのバトンを受けて、アンカーとして走る責任感と喜びがあるんです。」その声には、落語家としての誇りと覚悟が滲む。
観客の「スカウター」が見抜く稽古の深さ 春蝶にとって、落語はただ演じるものではない。
「お客さんって、ドラゴンボールのスカウターみたいなもの持ってるんですよ。何を見てるかっていうと、『お前、今日ここに来るまでにどれだけ時間かけたんや』って。一瞬でバレるんです。恐ろしいですよ。」
その言葉には、客席との真剣勝負の緊張感が宿る。
「高座は楽しい面接状態。準備が足りなかったら、平べったい話になる。朝から晩まで稽古して、休みの日の方がしんどいくらい。それでも、お客さんのスカウターに見透かされない芸を届けるために、時間と魂を注ぐんです。」
「紺屋高尾」に込めた思い
今回の春蝶の演目は「紺屋高尾」。江戸時代の吉原を舞台にした古典落語の演目で、江戸の吉原で名を馳せた花魁・高尾太夫と、紺屋(染物屋)で働く職人・久蔵の身分違いの恋物語だ。
「逆シンデレラストーリーですよ」と春蝶は笑う。
「職人が花魁に恋をして、運命が動き出す。権力も名声も持つ高尾太夫と、ただの職人の対比が面白い。」
この演目を選んだ背景には、春蝶自身の経験が色濃く映る。
「2011年から東京に住んでいるんですけど、大阪と東京の魅力って何かって聞かれるとドキッとして(笑)。ChatGPTに聞いてみたら、関西は歴史と伝統が深いって。確かに、藍染職人の歴史は江戸より100年早いんですよ。『紺屋高尾』を覚えたきっかけも、それを知ったから。」 春蝶は続ける。
「上方で職に就いていた人々が他の地域に移り、技術を広めたりコミュニティを形成したりしたと思うんです。特に東京のように多様な人々が集まる場所では、大阪の職人が集まって紺屋を営むなど、地域のつながりが重要だった。大阪の職人が活躍する設定を考え、自身の東京での経験や感覚を反映したネタを作りたいと思ったんです。大阪の職人が江戸で花魁と出会う設定は、僕が東京で感じた“よそ者”としての視点と重なる。異文化の中でどう生きるか。そこに投影できるネタをやりたかった。」
高座の上で、春蝶は大阪と東京の橋渡し役として、職人の魂を生き生きと描き出すのだろう。

3人の化学反応
桂吉弥と春風亭一之輔、二人の盟友について語る春蝶の声は熱を帯びる。
「吉弥くんは大人。僕が壁にボールを全力で投げて跳ね返ってきて泣いてるタイプだと(笑)、吉弥くんはそれを冷静に見てる。人間力の高さにいつも嫉妬しますよ。彼の芸は剣道の達人みたい。僕は砂をかけて戦う野戦タイプ(笑)。」
一方、一之輔については「粋でかっこいい侍」と評する。「じゃりん子チエの小鉄のようでもある(笑)。米2合と畳3畳でいい、みたいな執着のなさが、落語の庶民性とリンクしてる。今、一番良い落語家じゃないですか。」
3人の共通点は何かと問うと、春蝶は少し間を置いて答えた。
「“孤独”かな。敵は自分。孤独とどう付き合うか。それを乗り越えた先に、僕らの芸がある。」その言葉は、まるで高座の上で客席と対峙する瞬間を思わせる。
創作落語で伝えたい、命の重み
春蝶のもう一つの顔は、創作落語「桂春蝶の落語で伝えたい想い」だ。昨年芸歴30周年で10作目を迎え、今年は11作目としてペリリュー島の戦いをテーマにした新作「パラオの星」を披露した。
「1時間40分の大作ですよ。取材で現地に行って、3日間で23,000文字を書き上げた。書かせてもらっているという感覚でしたし、兵士の緊張感を、客席と一緒に作ってる感じ。」 戦争や差別、極限状態に置かれた人々の物語を通じて、春蝶は人間の深層に迫る。
「古典落語のため、と言ったら変だけど、極限の立場に立った人から学ぶことで、僕の人間が変わる。それが古典落語のセリフに乗る時、説得力が生まれるんです。」
例えば、特攻直前に妻を救おうとする男の物語。「命を懸けた愛情が、僕の人情話を演じる時の風景を変える。ウイスキーがシェリー酒の樽で熟成するように、僕自身がどこで熟成するか。それが大事なんです。」

51歳、父の背中と収穫期
来年1月、春蝶は51歳を迎える。父・2代目 桂春蝶が亡くなった年齢だ。「2025年7月に大災害が起きるなんて予言が話題になったでしょ(笑)。皆ハラハラしながら迎えてたじゃないですか。そんな感覚で、本当に俺、その年迎えられるのかなと思ったり……。父のその先を僕は知らないから、これまで自分が支えてもらってたものがフォッと抜けるっていう感じ。51歳って、父を知る最後の年齢。そこから先は未知の世界で、ちょっと怖い。」
父への思いを問うと、春蝶の声は静かになる。
「永遠の憧れ。追い続ける背中です。51歳を超えた時、父がこれをやってたのに、俺はまだこんなものか……って思うかもしれない。父との対話はこれからも続きます。」
だが50歳を過ぎた今、春蝶は「収穫期」の真意に気づいた。
「収穫期って、いい仕事をもらうことじゃないんだと。自分の思い通りに芸ができること。落語と一緒に歩けている感じがする。ワルツ、時にはタンゴを踊っているみたいに自由にリードできるようになった。」いまが一番楽しいと目を輝かす。
「戦争をテーマにした噺も自分がコントロールできているように思うんですよね。全員泣いていたり、全員どっかんどっかん笑ってるとか。落語家になって30年経ち50代を迎え、自分がこれまでやってきた結果みたいなものが一番いい形で見えてくると。」
さらにその先の理想もあるという。
「きっと65歳から緩やかにどれだけランディングしていけるか。優雅な着陸をしたいと思っていて。65歳までのこの15年間は自分の色濃いものをやっていっていいんだと思っています。」
今、聞き時の3人
「三人噺 2025」は、春蝶にとって特別な舞台だ。
「2022年から3回の公演を重ね、脂が乗り切った3人が、SkyシアターMBSで新しいお客さんに会える。歌舞伎でもこの世代が一番面白いって言うでしょ。努力のデータも、緊張の基準も分かってる。だからこそ、いい結果が出る。」
これまで全力で戦ってきた者にしか出ない言葉だ。 最後に、春蝶は笑顔でこう締めた。
「今、聞き時ですよ。食べ頃の3人です。お客さんのスカウターに負けない芸を、ぜひ劇場で感じてほしい。」 高座の幕が上がる瞬間、春蝶の「紺屋高尾」は、客席を江戸と大阪の歴史の交差点へと誘う。落語の魂が、3人の孤独と情熱を通して煌びやかに響き合うことだろう。

インタビュー・文・撮影:ごとうまき