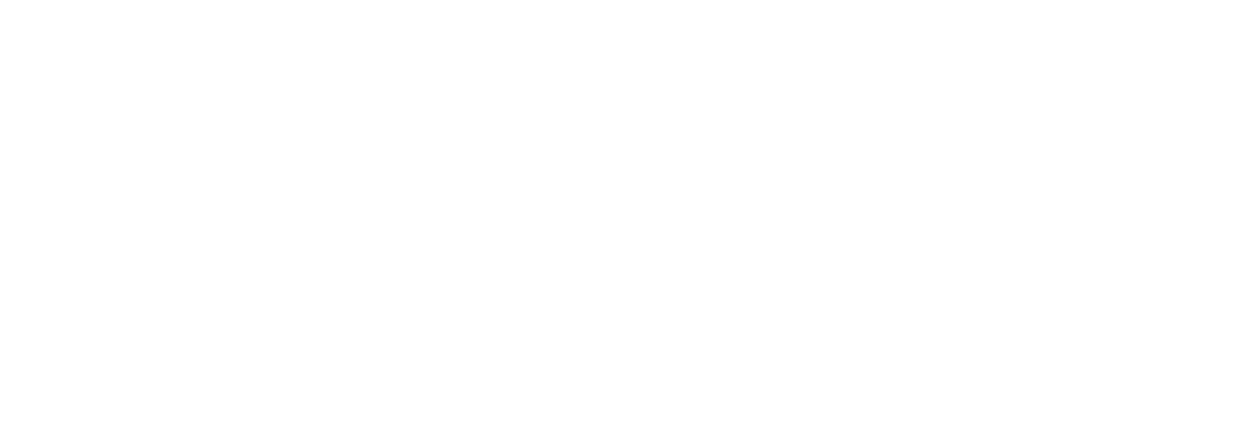落語界の異端児、二代目・快楽亭ブラック。
差別、借金、離婚、そして身内からの提訴。
被写体への「愛」が映画を面白くする
―― 本作を拝見し、


―― 師匠の中で特に印象に残っているシーンはありますか?

裁判すら「演出」に変えてしまう芸人の性
―― 撮影期間の6年半は、コロナ禍での配信開始や、




映画の神様に愛された「奇跡」の瞬間
―― 劇中、競馬で負け続けていた師匠が、

―― 師匠にとって、映画と落語はどのような存在なのでしょうか。

最近では、昔は馬鹿にしていた「人情噺」
「配信」では味わえない、映画館という体験
―― 最後に、これから映画を観る方へメッセージをお願いします。


【インタビュー後記】
取材の最後、写真撮影に応じるブラック師匠の佇まいは、どこか寂しげで、それでいて圧倒的に粋だった。 自身の不幸すらも「ネタ」という名の供物に変え、 高座に捧げ続ける。その姿こそが、 私たちが現代で失いかけている「芸人の矜持」 なのだと感じさせた。 インタビュー・文・撮影:ごとうまき