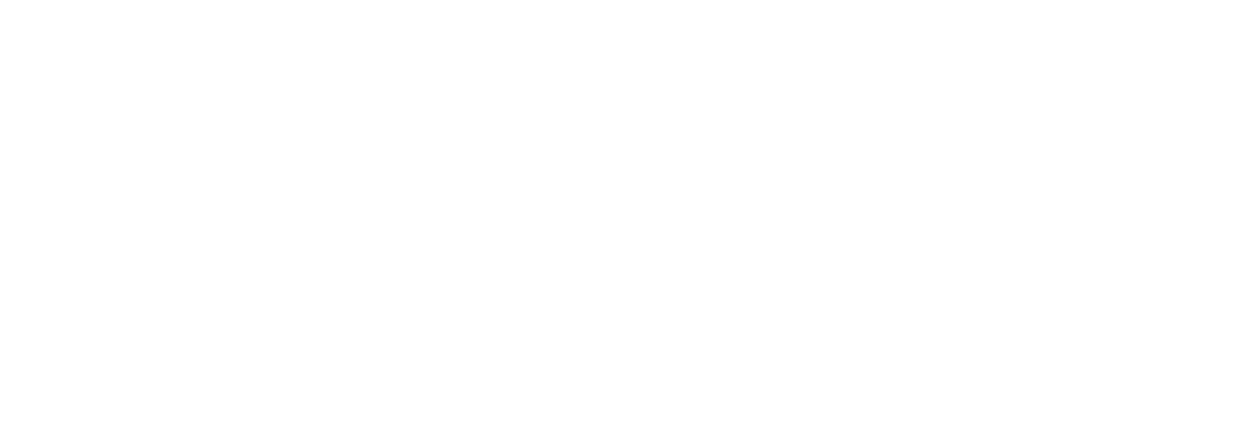「死にたい」はエゴか、「生きてほしい」は愛か。日本映画界に激震を走らせる衝撃作の核心に迫る。
もしも数年後の日本で「安楽死法案」が可決されたら——。在宅医として2500人以上の看取りに立ち会ってきた医師であり、作家の長尾和宏が、現場の切実な叫びを掬い上げ執筆した小説『安楽死特区』。この衝撃の物語を、名匠・高橋伴明監督と脚本家・丸山昇一がタッグを組み映画化。人間の尊厳、生と死、そして愛のあり方を問う社会派ドラマ『安楽死特区』が、2026年1月23日(金)より全国でロードショー。
物語の舞台は、国家戦略として設置された実験的施設「安楽死特区」。難病を患い余命半年を宣告されたラッパー・酒匂章太郎(毎熊克哉)と、特区の実態を告発しようと彼と共に潜入するジャーナリスト・藤岡歩(大西礼芳)。二人が施設で出会ったのは、それぞれに壮絶な覚悟を抱いた入居者たちと、命を導く医師たちだった。
今回、原作・製作総指揮を務めた長尾和宏氏と、主演の毎熊克哉氏による特別対談が実現した。「死」という、この国で長くタブー視されてきたパンドラの箱を、二人はなぜ開ける決意をしたのか。現役医師が抱くリアルな危機感と、一人の表現者が撮影現場で掴み取った「嘘のない真実」が、いま交錯する。
Contents
パンドラの箱を開ける――なぜ今「安楽死」を描くのか?
――現役の医師でありながらあえて「安楽死」という、日本社会では極めてセンシティブなテーマを小説にされた理由は?


――毎熊さんは、この重厚なテーマの作品で主演のオファーを受けた際、どのように感じられましたか?

「小手先の演技」への恐怖と、患者との対話
――毎熊さんは、章太郎という役をどのように構築していったのでしょうか。


――長尾先生、実際に完成した映画をご覧になっていかがでしたか?

日本独特の「一人称の欠如」と家族の在り方
――映画の終盤、驚いたのは実在の人物であるくらんけさんのインタビュー映像が挿入されたことです。劇映画の中にドキュメンタリーが入り込むという手法にはどのような意図があったのでしょうか。

――日本特有の死生観、ということでしょうか。

生と死を「ひとつながり」にする、ラストシーンのダンス
――毎熊さんに伺いたいのですが、作中の最後、霊柩車から降りて踊るシーンが非常に印象的でした。あのシーンを、毎熊さんはどう解釈されましたか?


40代を前にした「プレゼント」のような作品
――毎熊さんにとって、この『安楽死特区』という作品は、ご自身のキャリアにおいてどのような位置づけになりそうですか?

――最後にお二人から、これから映画をご覧になる方へメッセージをお願いします。



インタビュー・文・撮影:ごとうまき